July 01, 2005
組込みシステム開発技術展 2005
組込みシステム開発技術展に行ってきました。その感想とおみやげについて書いてみます。
総括をいうと、期待していたほど目新しいものがありませんでした。以下、箇条書き。
- RenesasのSH-2Aを期待して行ったのですが、SH-TinyとかSH-4Aはあったのですが、SH-2Aはなく残念。
- MEMSもあまりなく、富士通メディアデバイスの1軸ジャイロ(カーナビ用)と3軸加速度計がおいてある程度でした。富士通の方から説明を色々受けましたが、3軸加速度計の商品化はまだ時間がかかるようです。サンプルがでたら早速手に入れて試験にかけてみたいと思います。
- ARMも興味があったので覗いてみました。ARM9のAD変換がついたマイコンライクなものありませんかと聞いてみたところ、あるらしいですが、製造社名を忘れてしまいました…。
- 組込み用データベースが盛況でした。マイコンやストレージの進化の賜物ではないでしょうか。2D検索もできるものもあったりして、カーナビの地図検索はこういったものを使うと簡単に実現できそうです。
- MatlabはSimulinkで倒立振子をやっていました。パソコンでブロック線図を書くだけで実際の機器が制御できるのは、教育用とかにうってつけだと思います。マイコンは普通の人にとっては敷居が高いようですし。
- 昨年紹介した小型ボードの会社のiCOPは新製品を出していました。Vortex86-6077という製品で533MHzのCPUが載りながらも99 x 96 mm。しかもお値段ほげ万円とか、一枚欲しいなぁ。
お土産編。

一番よかったのはAnalog Devicesの水筒。

あとはNECの『バザールでござーる』のうちわ。最近見かけませんね。

不明なのはMatlabの立方体。枕になるかと思いましたが駄目でした。何用なのでしょう?
その他いろいろともらいました。
July 05, 2005
Google Toolbar 3β
最近気づいたのですが、Google Toolbarの新しいのがでていたみたいです。といってもまだベータ版ですが。
『マウスオーバー辞書』といういけている機能がつきました。マウスをわからない英単語の上にもってくると、訳を表示してくれるという機能です。英語が得意でない僕にとってもとってもいけている機能だと思います。
いろいろ試してみたのですが。ある程度の難しさの単語までは訳が表示されるようです。辞書は内蔵のようで、単語を調べたりするごとにネットにつながるわけではないようです。(逆につながってどんどん辞書が拡張されたら面白いと思うのですが。)
マウスオーバー辞書というとこんなのもあります。Pop jisyo.comというので、辞書をつけてほしいページのURLを指定すると、マウスオーバー辞書付のページが表示されます。例えばGoogle Newの英語版で試すとこのような感じになります。HTMLをみると面白いですね、力技で解決してあります。
July 06, 2005
M-Ⅴ 6号機 打ち上げ延期
本来なら今日が宇宙研のロケットM-Ⅴ 6号機の打ち上げ予定日だったのですが、悪天候のため延期されてしまいました。残念です。
悪天候とのことですが、宇宙研の先生の話によると予測された気象条件とあわない場合もNGらしいです。これは打ち上げ前に打ち上げ日の天候を予測して、色々とプリセットする必要があるためらしいです。今回はどうやら本当に悪天候だったらしいですが。
延期された結果、打ち上げは8日以降になるということ。友達も何人か現地入りしているようですが、大丈夫でしょうか。一度は生打ち上げを見てみたいものです。
July 10, 2005
July 14, 2005
RubyでFFT
レポートでフーリエ変換をどうたらしなければならないので、FFTをRubyで実装してみることにしました。といってもRubyという時点で金持ちプログラミング決定なので効率無視です。
Cooley-Tukey 型 FFTで実装してみました。これよりも効率のよいPrime Factor 型 FFTというのもあるのですが(詳しくはFFTの概略と設計法参照のこと)、因数分解とかがぱっと実装思いつかなかったので、簡単なCooley-Tukey 型にしました。
コードは続きをどうぞ。改善の余地がかなりあると思います。
続きを読む "RubyでFFT"July 16, 2005
ロボットのプログラム
よく読む機械屋大学生さんのブログにロボットのプログラムで『switch~caseで条件分岐を書いてうまくいかない』という記事が書いてあったので、それについて思うことがあるので語ってみようと思います。
結論からいうと、ロボットみたいな分岐の多いプログラムはifやswitchをできるだけ少なくしたほうが資産価値が高いコードだと思います。とりうる分岐が多くなるごとにifやswitchが入っていると、後から読んでわけのわからんコードが増産されることになります。悲惨な場合はifやswitchがあるのに関わらず、関数や定数使わずコードに1とか2とかがベタ書きしてあるプログラムの場合で、そんなコードは捨てたくなります。
(方法論については続きをどうぞ)
続きを読む "ロボットのプログラム"July 19, 2005
今更ながらADXRS150
Analog DevicesのMEMSジャイロ、ADXRS150を使いたいのですが、パッケージがBGAということで今まで食わず嫌いしていました。しかし、気づいてしまったのです。BGAであっても外周のパッドだけで全信号がとりだせることを。
ということはパッドをパッケージの外側まで引き出しておいて、そこから低融点半田かなんかを流し込んでやれば半田付けできるのではないかと思っています。ということでADXRS150のEAGLEのライブラリを作ってみました。
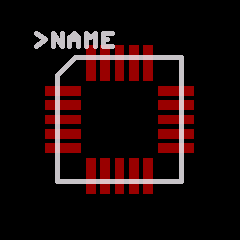
こんなパッド形状です。
July 21, 2005
W-sim
Willcom(旧H"といったほうがわかりやすいでしょうか)のPHSモジュール、W-simのカンファレンスに行ってきました。
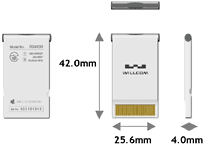
W-simモジュール。
コンセプトとしては『どんなものにでも音声・情報インフラを!!』ということだと思います。今まではコストが見合わないとか、通信機器を独自開発するのが面倒だ、といった理由から通信装置が組み込まれることを敬遠されてきた製品に対して、PHSモジュールという救いの手が降りてきたという感じではないでしょうか。簡単にいうとオレ様仕様携帯ができるということです。
また、ロットが5000~1万、あるいはそれ以下の少量機器にも視野にいれている、とのことでした。秋月系の人達にもうまくいったら人気がでるのではないでしょうか。
技術的な話になりますが、インターフェイスはシリアル+PCM音声といった感じの独自なものでした。シリアルで使えるというのは非常にいけていると思います。
とりあえず早急に開発キットを提供してもらえないかなと思います。あの無人機、携帯電話網使っていますから、PHS特有の通信コストが定額になるとかは非常に魅力的です。携帯大国、日本に生まれてよかったと本当に思います。
July 26, 2005
みんな大好き塊魂

『みんな大好き塊魂』、PS2ゲーム『塊魂』の続編です。発売日に買うという気合の入ったことをしてしまいまうぐらい、期待度大なゲームでした。ということでレビューしてみます。
操作方法は前作と変わらず、『ふんころがし』の要領で塊を転がして物を引っ付けて塊を大きくする、ただそれだけ。ひたすら飽きるまで転がします。
で、転がしつづけました。前作よりもレベルが上がっています。クリア条件をみたすことができず、『王様』にレーザービームをくらうことが幾ばくと。ステージもバリエーションが増えて面白いくなっています。個人的にはクッキーやお花がたくさん集まるステージや自動車で高速移動のステージが楽しいです。あと、そうだ、最大塊直径も前作をしのぐものがありますよ。で、でかい。
July 27, 2005
STS-114 Launch!!

STS-114(スペースシャトル ディスカバリー)打ち上げ成功、おめでとう!! (写真は© NASA)
長かった沈黙をやぶり、とうとう打ち上げられました、スペースシャトル。感動のあまりTVの前で涙しそうになりました。
打ち上げ延期の原因になったセンサーの異常は原因解決されていないものの特に異常がみられなかったようで、そのまま打ち上げという運びになったようです。打ち上げは、外部燃料タンク切り離し直後もスラストを使っていないことから、順調そのものだったと思います。
今回から外部燃料タンクの切り離しを確認できるように、新たにタンク上部にカメラがつけられたのですが、そこから見えた映像はものすごく鮮烈でした。タンクから上昇していくオービタ。そしてその後ろには地球のまんまるな淵がはっきりと確認できる。やっぱり宇宙はいいですね。宇宙から地球を是非みてみたい。
July 29, 2005
STS-114 断熱材剥離
STS-114(スペースシャトル ディスカバリー)ですが、打ちあがったはいいものの、断熱材の剥離問題が解消しておらず、次回以降のフライトが無期限延期になってしまったようです。
現在の調査によると幸い今回はオービタ本体に損傷をあたえることはなかったものの、NASAの公式発表によると、剥離した断熱材の大きさは『24 to 33 inches long, 10 to 13 inches wide and 2-1/2 to 8 inches thick(長さ 61~84 cm、幅 25~33cm、厚さ 6~20cm)』とのことでした。結構派手にはがれてしまったという感じではないでしょうか。剥離した部分は外部タンクの断熱材の一部で、きれいな円筒形の曲面の部分ではなく、空力的に影響をうけやすい飛び出た部分であったようです。
前回の事故で問題が指摘されていた部分であるだけに、それが改善されていなかったというのはかなりショックなことではないのでしょうか。やはり物作りというのは一筋縄ではいかないことばかりのようです。これを機に無期限延期を決めたのもよい決断ではないかと思います。
しかしながら、転んでもタダではおきないではないですが、上手くいっていないことをモニタリングする技術が実証されたのは貴重なことだと思います。実物を作るとデバックは非常に困難を極めますから…。
動きとしては、ISS(国際宇宙ステーション)にドッキング成功しました。また、船体の安全確認のためにISSから全周映像をとったようです。オービタをISSの下で一回転させるというなかなか難しいことをしていました。
| « | July 2005 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||












